 句読点の歴史 句読点の歴史
|
| 日本語の句読点や符号の使い方については何故か明確な定めがありません。昔は,日本語の文章に返り点といった符号のようなものはありましたが,語句や文の区切りに用いる句読点はなく,句読点が登場するのは明治時代になってからで,海外の文書情報として,様々な符号と共に入ってきました。よって,最初の句読点は英米語などと同じ「.」と「,」だったと考えることができます。しかし,日本語は元々縦書きでしたから,そのスタイルに合う句読点として「。」と「、」が新たに登場したのだろうと思います。そうすると,どの句読点を使うか煩雑になり,書き手によって違うという事態が起こりますから,その使い方を統一しようという考えが生まれます。そのころ,1906年(明治39年)に文部省図書課が「句読法案」を出し,1946 年(昭和21年)には文部省教科書局が「くぎり符号の使ひ方(句読法)案」を出しますが,残念なことに,いずれも句読点の使い方をしっかり定めるものではありませんでした。その後,1951年(昭和26年)に国語審議会が作成した「公用文作成の要領」の中で,横書き用の句読点を「。」 と「,」にしようと提案し,内閣府もそれを勧めた結果,公文書の日本産業規格として採用され,教育の分野で「学習指導要領における表記」として横書き用の句読点は「。」と「,」にするということになりました。実際に,理科,社会,算数,数学など横書きの教科書に用いている 句読点は「。」と「,」で,国語など縦書きの教科書では「。」と「、」を用いています。ただ,内閣府の勧め(内閣府令)は法的拘束力がないため,ほとんどの省庁が従わなかったという経緯もあり,句読点の使い方は統制が取れないまま,2022年に改めて作成された「公用文作成の考え方」では,句読点は「。」と「、」を基本とし,横書き用の読点には「,」を用いても良いという,書き手に委ねる基準を提示しました。 |
| 日本語の文章には縦書きと横書きがありますから,句読点もそれなりに使い分けるほうが賢いライティングに繋がります。しかし,横書きの文章に用いる読点は「,」と「、」のどちらでも良く,ライターの自由ということになっています。一般的にはそれで良いのでしょうが,特殊なライティングでは表記・表現を一貫させるのが原則であるという概念があることから,少なくとも専門分野ごと,あるいはメディカルライティングやテクニカルライティングといった領域ごとで句読点の用法を統一することが理想的でしょう。メディカルライティングの領域では,1951年の「公用文作成の要領」で提案された横書き用の句読点の組み合わせである「。」と「,」が広く用いられるようになっているという印象を受けています。 |
| |
 句読点以外の符号について 句読点以外の符号について |
| 日本語では,句読点以外の符号である ;,:,―,",’,( ) などに関する用法はほとんど決まっていません。しかし,符号はライティングの際にとても便利なツールであるとともに,文字と同じように独自の意味を持っていることを考えると,日本語でのそれらの用法が確定するまでは,符号の由来元である外国語,特に英語での用法に倣って用いることが得策であると考えています。 |
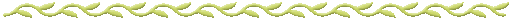 |